ボウケンレイダー
-The Sharp Venturer-
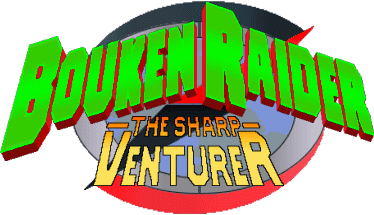
「Here you are」
そう差し出された小箱を、女は両手で受け取った。風光明媚な保養地として有名な南仏・ニース。その高級ホテルの一室であり、開け放たれたバルコニーの先には、「コート・ダジュール(紺碧海岸)」の名にふさわしい美しい地中海が広がっている。
「開けてもいい・・・のよね?」
「ああ、もちろんだとも」
そう許しを得てゆっくりと小箱を開くと、女の顔に見る間に満面の笑みが広がっていった。
「わぁ・・・素敵・・・!」
女が小箱から取り出したのは、中央に巨大なエメラルドをはめ込んだ、細密な彫刻の施された黄金のネックレスだった。
「アッバース朝時代のカリフが身に着けていた代物だ。普通なら博物館でしかお目にかかれないだろうな」
「いいの? そんなものをもらっちゃって・・・」
「宝石はその輝きで女をより輝かせるためにある。そいつは博物館のショーケースの中なんかじゃなく、君の胸で輝いている方がふさわしいのさ」
そう言われると、女はネックレスを身に着けて見せた。
「どう・・・かしら?」
「あぁ、やっぱりそうだ。そいつは1000年以上の時をかけて、ようやく本来の持ち主のところにたどり着いたんだな」
笑いながらそう言う男は、20代後半ぐらいの白人の男。伸ばした金髪を首の後ろで束ねており、ハンサムではあるが、少々目つきが悪い。
「気に入ってもらえたかな?」
「気に入らないなんて言ったら罰が当たるわ。でも・・・手に入れるのに、すごく苦労したんじゃないの?」
「まぁね。だが、お宝を手に入れるのに危険はつきものさ。それに俺にとっちゃ、その危険も人生を楽しくするスパイスだからな。もっとも、君のように魅力的な女と触れ合うのも、俺にとってはいつだって大冒険だがね」
そう言いながら女に近づくと、男はその体を抱きすくめた。
「あなたって、本当にすごい冒険家なのね・・・」
「初めて会ったときは信じてくれなかったくせに。だから証拠を持ってこなけりゃならなかった」
「それは謝るわ。でも・・・おかげでますます、あなたについて知りたくなったわ。ねぇ、聞かせて頂戴。あなたのしてきた冒険の話・・・」
「あぁもちろん。君さえよければたっぷりと聞かせてやるよ。ただし、ベッドの上で・・・ね」
そう言って女の腰に手を回し、ベッドルームへと誘おうとする男。
「あん、まだ明るいのに・・・」
女もまた、まんざらでもなさそうな顔をしながら、それに応じようとした。そのときだった。
ビビビ、ビビビ、ビビビ・・・
「「!?」」
不意に響き渡ったアラーム音のような音が、一瞬にしてそのムードをぶち壊した。女が見ると、どうやらその音は男が右手首につけている腕時計のような器具から発せられていた・・・が、男がものすごく不快そうな表情を浮かべて素早くその器具のボタンを押すと、音はおさまった。
「それ・・・携帯電話か何か? 誰かから呼び出されていたんじゃないの?」
「いや、なんでもない。どうせ大した用事じゃないんだ。さぁ、早くこっちへ・・・」
強張った笑顔を顔に浮かべながら、強引に元のムードを取り戻そうと取り繕う男。そこへまた、再びあの音が響き始めた。すかさず男は再びそれを止めようと、ボタンに手を伸ばしたが・・・
ババババババババババ!!
「ギャアアアアアアアアアッ!?」
「キャアアアアッ!?」
突如、男は全身に電流が走ったかのように身もだえしてバッタリと倒れ、女は悲鳴を上げた。
「ちょ・・・何!? ねぇ、大丈夫!?」
慌てて男に駆け寄る女。だがそのとき、男の右手首の器具の文字盤にあたる部分から光が放射され、その中にCGで作られたキャラクターの3D映像が浮かび上がった。
『驚かせて失礼。緊急の業務連絡なのでね』
逆さにした円錐に目鼻と口、それに二本の腕と思しき針金のような黒い棒がついているといった外見のそれは、事務的な口調で彼女にそう言った。その瞬間
「何しやがるこのトンガリ野郎!!」
男がガバリと起き上がり、噛みつかんばかりの勢いで3D映像のキャラに怒鳴った。
『仮にも上司に対してその言いぐさは感心しないな。そもそも、君が悪いのだよ。君がたびたび私の緊急コールを無視するから、このあいだのメンテナンスの際にレイダーブレスにこのような仕掛けを施さねばならなかったのだ。まぁ、そんなことはどうでもよい。仕事だ』
「嫌だ」
男はきっぱりと言った。
「俺は確かにあんたに5日間の休暇申請を出して、そして受理された。今日はまだその一日目、それもようやく半日過ぎた頃だぞ」
『あぁ、確かに私は休暇の許可を出した。だが、私が君の事情を斟酌したところで、ネガティブどもも同じように斟酌してくれるわけではない。君が確実に休暇を満喫したいのであれば、全てのネガティブどもを叩き潰すしかないだろう。もっとも、その時は同時に君もサージェスでの仕事を失うことになるだろうがな』
「だからって、何で俺を呼び出す! ほかにもエージェントはいるだろうが!」
『サージェス・ヨーロッパの人的資源も無限ではない。生憎、活動可能なエージェントは全て出払っている。こういうときのための遊撃戦力として自分が雇われていることを忘れたわけではあるまい』
罵り合いにも似たやり取りを繰り返す両者。
「えーと・・・なんだかよくわからないけど、急なお仕事みたいね。残念だけど、また今度ゆっくりできる時間が取れたら連絡してね」
「あ! おい、ちょっと待てって!」
「宝石、本当にありがとうね。次のショーには絶対に着けて出るから。それじゃあね」
そう言うと女はバッグを手にして、部屋から出ていってしまった。がらんとしたホテルの一室に、沈黙が流れたが・・・
「出ていっちまったぞ! どうしてくれるんだ!?」
『別に今日でなければならないということはないだろう。また休暇をとって誘えばいい』
「そう簡単にいくか! あの子はただの女じゃねぇ、パリコレにも出てる引っ張りだこのスーパーモデルなんだぞ! 今日だってスケジュールを合わせてもらうのにどんだけ苦労したか・・・」
『そうかね。だが、君は自分の仕事の重みについてもっと自覚するべきだ。君がそうしてスーパーモデルと逢引きができるのも、全ては平和あったればこそのものだ。そしてその平和は、ネガティブどもにプレシャスの悪用を許せばいとも簡単に崩れ去ってしまう』
男はさらに言い返そうとしたが、このまま続けたところで話は平行線をたどるだけだと思い直し、その言葉を呑みこんだ。そして
「・・・二日だ。これが終わったらもう二日プラスしたうえで、改めて休暇をもらう。今度は何があろうと最後まで休むからな」
『私としては結構だ。まぁそれを全て消化できるかどうかは、ネガティブたちの動向次第だがな』
「チッ・・・それで? どこへ行って、どいつをぶちのめして、何を奪い返して来ればいい?」
『的確な質問だ。まずは、何を奪還すべきかだが・・・』
CGのキャラの姿が消え、代わりに別の立体映像が浮かび上がる。映し出されたのは、一見して簡素な見た目の横笛だった。
「笛?」
『「ドルイドの魔笛」、そう呼ばれているプレシャスだ。モーツァルトの「魔笛」を見たことは?』
「一度だけある。ガキの頃、親父の都合でコヴェント・ガーデンに連れていかれてな。オペラにしちゃそんなに難しい話じゃないし、そこそこ楽しめたが。あれに出てきた魔法の笛は、吹くと森の動物たちがぞろぞろと出てきたが、そんな力があるプレシャスなのか?」
『いや、モーツァルトがその笛の話に触発されて「魔笛」を書いたという説はあるが、その力はオペラに出てくる魔笛よりももっと強い。その笛の音にはあらゆる動物を、一度に大量に操ることができる魔力がある。我々はこのプレシャスの確保に成功したが・・・プレシャスバンクへの移送中に、強奪されてしまった』
「なんだよ、要するに身内の失態の尻拭いじゃねえかよ。ますます気が乗らねぇが、相手は誰なんだ?」
『「カルタヘナ・カルテル」だ。君も名前ぐらいは聞いたことがあるだろう?』
「確かコロンビアのマフィアだったな。他の組織との勢力争いで押され気味になってきたもんで、何年か前から新しいシノギにネガティブの真似事に手を出したっていう・・・そんな半端な奴らに、プレシャスの強奪を許したのかよ」
『我々もそう奴らの戦力を過小評価していた。だが奴らは完全な奇襲で輸送チームを襲撃し、輸送にあたっていた職員を皆殺しにして、「ドルイドの魔笛」を奪っていったのだ』
「しくじったな、ミスター・ボイス。まぁ話は分かった。そいつらは今、何処にいるんだ?」
男がそう言うと、今度は一隻の貨物船らしき船と、世界地図が3Dで表示された。
『「カラマール号」。奴らが南米と欧州との間での密輸品の密輸に使用している偽装貨物船だ。この船に奴らが「ドルイドの魔笛」を持ち込んだことがつい先ほど明らかになった。既にこの船は、コロンビアの港まで12時間の位置まできている。ゴーゴーガレオンで急行し、入港する前に「ドルイドの魔笛」を回収してほしい』
「了解した。それだけ聞けば十分だが・・・念のため、連中の処遇についても聞いておこうか」
『いつも通り、君の判断に任せる。だがそうだな・・・自分たちが手を出した稼業が、いかに割に合わないものか、今後のために奴らに思い知らせるのもよいだろう』
「わかった。あとは任せな」
『頼んだぞ、ボウケンレイダー』
そう言って通信を切り、クローゼットへと近づくと、その男・・・アーサー・V・ドレイクはそこに収められていた緑のジャケットに袖を通した。
轟轟戦隊ボウケンジャー外伝
ボウケンレイダー
-The Sharp Venturer-
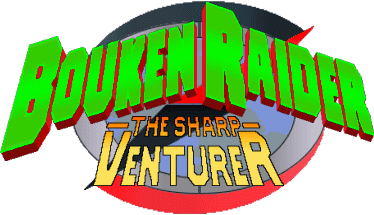
Task.1 黄金の邪竜
−同日 PM:20:06 大西洋上−
夜の闇に染まった大西洋の大海原の上を、一隻の貨物船が静かに航行している。風はなく、波は凪いでいるが、空は一面鉛色の雲に覆われ、星も見ることができない。と・・・
ゴゴゴゴゴゴ・・・
貨物船の上に、その大きさをさらに上回るほどの影が、ゆっくりと覆いかぶさってきた。
影の正体は、巨大な船であった。見かけこそ大航海時代のガレオン船を模してはいるが、その全体は金属で覆われている。そしてそれがただの船ではないなによりの証左に、船は貨物船の上に張り付くように、悠然と飛行していた。
「目標を確認した」
その甲板の際すれすれに立ち、貨物船を見下ろしながらドレイクは言った。すると、右手に着けたレイダーブレスから光が発せられ、その中に様々な情報が表示される。
『こちらで推測した敵の人員数とその装備だ。君の脅威となるようなものではないだろうが、くれぐれも慎重にな』
「そいつはどうも。大した冒険にはならないだろうが・・・ま、行ってみっか」
そう言うと男はそのまま体の重心を前に傾け
「Entryyyyyyyyyyy!!」
ふわりと甲板から飛び降りた。ものすごい風圧が下から上へと吹き付ける中、貨物船がぐんぐんと視界に迫っていく。そしてドレイクはおもむろにレイダーブレスのボタンに指を駆けると、呟くようにコールした。
「スタートアップ」
その瞬間、ドレイクの体は緑色のまばゆい光に包まれ、一秒にも満たないのちに、その姿は全く別なものへと変化を遂げていた。
頭部全体を覆うヘルメット。その顔面にはYの字に似た形状のバイザーがあり、その上には車のヘッドライトを思わせるライトがついている。全身も一体型のスーツによって包まれており、体の中心線部分は白、その左右の側部はダークグリーンに塗り分けられている。そしてその胸の中央には、羅針盤をモチーフとしたサージェス財団のシンボルマークが大きく描かれていた。
変身を遂げたドレイク・・・いや、サージェス・ヨーロッパ所属プレシャス回収専任エージェント、コードネーム「ボウケンレイダー」は、落下する空中で両膝を抱え込むと、体を丸めた状態でグルグルと回転させた後、姿勢を飛び込み選手のようなものに変え、頭から海面へと真っ逆さまに落下していった。そして・・・
バシャァァァァァァン!
完璧に計算し尽くされた突入角度によって、飛び込みの際の音と水しぶきは最小限のものに抑えられた。ボウケンレイダーは海中へと潜ったまま、両足裏と両袖に仕込まれた小型スクリューを起動し、音も立てずに貨物船へと近づいていった。
ボシュッ!
貨物船に近づくと、ボウケンレイダーは腰からスコープショットを取り出し、磁石式ワイヤーを発射した。狙い過たず、ワイヤー先端のマグネットは甲板の手すりにくっついたところで、ボウケンレイダーはスコープショットの内臓ウィンチを起動し、貨物船の甲板上へと自らの体を引き上げた。
「まずは潜入成功、っと・・・」
軽い口調でそう呟きながらも、視覚と聴覚だけでなくセンサーも動員し、甲板上の状況を探るボウケンレイダー。その結果明らかになったのは、「甲板上には誰もいない」ということだった。
「妙だな。巡回の見張りぐらいいてもよさそうなもんだが・・・」
安堵よりも警戒の意識を強くし、ボウケンレイダーは腰のホルダーから引き抜いた大型ナイフ・ダッシュナイダーを右手に構えると、慎重に足を踏み出した。そのまま甲板上の通路やコンテナの間を横切りながら移動していくが、やはり全く人の気配がない。そのまま移動を続け、やがて彼は船内へと続く階段を発見した。彼は足音を立てないように慎重にそれを下りると、一度足を止めた。
「・・・」
静かすぎる。聞こえてくる音と言えば機関室のエンジン音や各所に設けられたファンといった機械の発する音ばかりで、人の話し声や人のたてる物音は一切聞こえてこない。船内の人間が寝静まるにはまだ早い時間である。
「しょぼい任務かと思ったが・・・」
漂い始めた不穏な気配に、警戒心が強まると同時に、「冒険」を・・・「危険」を求める心が、ゆっくりと頭をもたげてくる。マスクの下の口の端を笑みで吊り上げながら、彼はゆっくりと足を進め始めた。
「・・・!」
と、真っ直ぐ行った先にあるT字路に、ボウケンレイダーはあるものを認めた。T字路を左に曲がる角の先から、通路の上に何かが流れている。映像を拡大するまでもなく、それが血であることはすぐにわかった。同時にその角を曲がったすぐ先に、センサーが2つの熱反応を捉えた。一つは通路の上に倒れており、体温はほぼ失われつつある。おそらく、あの血の主であり、今まさに息絶えようとしているのだろう。そしてもう一つは、倒れている人間の足元に立っている。その反応の示す熱量が、明らかに通常の人間を超えていることに、ボウケンレイダーは少し驚いた。が、すぐにホルスターからエネルギー拳銃・カイシューターも引き抜き、ダッシュナイダーとともに構えながら、慎重にT字路へと足を運んで行った。そして・・・
「Freeeeeeeze!!」
叫びながら銃口をそれに向けたボウケンレイダーだったが、意に反して固まったのは、彼の方だった。
そこに立っていたのは、全身を赤い鱗で覆った異形の怪人だった。トカゲを人間大にして直立二足歩行させたような姿であり、両手は五本の指を備えており、その右手には血の滴る蛮刀を携えている。その足元には、背中に大きな刺し傷のある南米系の男が転がっていた。
「グギャァァァァァァッ!!」
トカゲ怪人はすぐさま振り向き、蛮刀を振りかざして襲いかかってきた。こちらに振り返ったその頭は、トカゲというよりは肉食恐竜のような凶悪な面相である。先制をとられる格好となってしまったボウケンレイダーだったが、不覚を演じるのはそこまでだった。
「・・・」
振り下ろされた蛮刀を軽々とかわすと、彼はその動きでトカゲ怪人の背後へと素早く回り込み、左手でトカゲ怪人の口をふさいだ。それと同時に
ザシュッ!!
ダッシュナイダーの刃をトカゲ怪人の喉笛に押し当て、一気に引き切った。ざっくりと口を開けたトカゲ怪人の喉笛からおびただしい血液が噴射し、通路の壁を真っ赤に染めていく中、ボウケンレイダーは断末魔の絶叫を上げるため開こうとする口を完全にふさいだ。そして、血液の噴出が収まり、その体から完全に力が失われると同時に、トカゲ怪人の体を通路に投げ出した。
「不覚だったぜ。まさかこんな奴が出てくるとは、さすがに想定外だった。しかし、こいつは・・・」
ボウケンレイダーはそう言いながら、レイダーブレスを操作してサージェス・ヨーロッパのデータベースにアクセスすると、心当たりのあるデータと目の前のトカゲ怪人のデータの照合を開始した。相対したとき一瞬動きを止めてしまったのは、相手が異形だったからではない。そんなものはトレジャーハンターになって以来、とうの昔に見慣れている。ボウケンレイダーが驚いたのは、それが彼の認識の中では、「既にいないもの」だったからである。
やがて数秒と待たぬうちに、データベースとの照合結果は「100%合致」という結果で表示された。
「さぁて、おかしなことになったな。こいつらはとうの昔に、明石のチームが全滅させたと思ってたんだが・・・」
ボウケンレイダーがそう首をひねった、そのときだった。
「うわぁぁぁぁぁぁっ!!」
ドンドンドンドン!!
通路の向こうから銃声と共に、錯乱したような男の絶叫が聞こえてきた。ボウケンレイダーはそれを耳にすると、すぐにその声の方へと駆け出した。
絶叫と銃声の元へと通路を駆けるボウケンレイダー。アクセルスーツのブーツは静音性をいかんなく発揮して、高速での疾走でもほとんど音をたてることはなかった。途中の通路にもまた、何人もの男たちの死体が転がっており、そのいずれにもあのトカゲ怪人の蛮刀によるものと思しき傷がついていた。
やがてボウケンレイダーは通路の突き当りにあった狭い階段をひと跳びで飛び上がり、音もなく着地するとその先にある部屋の出入口の影に身を潜めた。そこは船の中心ともいうべきブリッジであり、センサーはその内部にいくつもの熱源を捉えているうえ、部屋の中からは何者かの話し声が聞こえてきていた。
『陛下。お探しの「ドルイドの魔笛」にございます』
『うむ』
ボウケンレイダーは聴覚センサーの感度を上げ、中から聞こえてくる声に耳をそばだてた。
『見た目は何の変哲もない笛だな。だが感じるぞ、確かな魔力を。これならばアレを操ることも可能となろう』
『おめでとうございます、陛下。これで先王の代よりの悲願である、我ら竜が世界を支配する日も目前のものとなりましょう』
『喜ぶのはまだ早いぞ。これはまだ第一歩・・・アレを御するための術を手に入れたにすぎぬのだ』
『ハッ、承知しております。次はいよいよ、「魂」を・・・』
『そのとおりだ。だがその前に、先王と同じく余にもまた、邪魔をしようとする者がいるらしい。 ・・・薄汚いドブネズミめが、そんなところで聞き耳を立ておって。余が気づいておらぬとでも思ったか!』
「・・・やれやれ」
マスクの下に苦笑を浮かべながら腰を上げると、ボウケンレイダーはぶらりとした足取りでブリッジの中へと足を踏み入れた。
「バレちまったんじゃあしかたねぇ。しかし妙だな、お前たちは全滅したって聞いてたんだが・・・」
そう言いながら、ボウケンレイダーは目の前に並ぶ異形の者たちを眺め渡した。その足元には、惨殺された「カルタヘナ・カルテル」の男たちの死体が転がっている。
「なぁ、ジャリュウ一族」
異形の者たちはいずれも、あのトカゲ怪人と同じく、全身を鱗で覆った恐竜と人間を混ぜ合わせたような容姿をしていた。既にボウケンレイダーは、この異形の者たちの正体を看破していた。その名は、ジャリュウ一族。かつてサージェス財団とプレシャスの争奪戦を繰り広げたネガティブシンジケートの一大勢力であり、恐竜と人間の遺伝子を組み合わせて生み出されたキメラの一族である。プレシャスの力を利用して自らが人類にとって代わり世界を支配しようと目論んだ彼らは、サージェス・ジャパンのボウケンジャーと幾度も戦った末、2007年に壊滅した・・・はずであった。
「おのれ、無礼な! リュウオーン二世陛下の御前であるぞ!」
異形の者たちの一人・・・黄金の鎧をまとい、プテラノドンにそっくりの頭をして、両腕が皮膜でできた一対の翼となった怪物が、ボウケンレイダーを咎める。
「リュウオーン・・・二世だと?」
その名にボウケンレイダーは首を傾げた。リュウオーンというのはかつてのジャリュウ一族の長の名前であり、ドレイクもよく知るボウケンジャーのリーダーとの決戦に敗れ、落命したと聞いている。
「かまわん、ゴードン。どうやらこやつは我らとの因縁深いあのサージェスの手の者らしい。ここで我らの復活を知らしめておくのもまたよかろう」
そう言いながら、リュウオーン二世と呼ばれた怪物が一歩進み出る。確かにその怪物は他のトカゲ怪人たちよりも一回り大きな体を誇り、外見もデータで目にしたことのあるリュウオーンによく似ていたが、リュウオーンとは異なる点も見受けられた。頭には5本の角のついた兜をかぶり、右手には鋸のようにギザギザした刃の付いた大剣、左手には2本のスパイクの付いた盾をそれぞれ手にしている。そしてティラノサウルスそっくりの恐竜の頭が、そのまま右肩と融合してくっついていた。
「余の名はリュウオーン二世。先王の名を継ぎ、ジャリュウ一族の長となった。こうして対面することになるとは、よくよく貴様らサージェスとは因縁があると見えるな」
「知らねぇな。前の王様を殺ったのは俺じゃねぇ。かたき討ちをしたいなら他を当たってくれ。 ・・・それ以前に、滅んだはずのお前らがどうしてこんなところにいる?」
ボウケンレイダーがそう言うと、リュウオーン二世は口の端をゆがめてにやりと笑った。
「我らが滅びただと? 見当違いも甚だしいわ。確かに貴様らによって先王は倒され、我らは滅びの危機に瀕した。だが、我らは全滅したわけではなかった。そして賢明なる先王は、このような危機を予期して手を打っていたのだ」
「なんだと?」
リュウオーン二世の言葉に、ボウケンレイダーは思い当たる節があった。確かにボウケンジャーはリュウオーンを倒し、ジャリュウ一族は壊滅した。だがそれはジャリュウ一族の「全滅」を意味するものではなかった。リュウオーンの死後も、最下級兵士であるジャリュウ兵・・・あのトカゲ怪人が数体ではあったが、生き残りの存在が財団本部には報告されていたのである。無論、サージェス財団としてもこの報告を無視するつもりはなかったが、ボウケンジャーの活躍によっていくつものネガティブシンジケートが壊滅に追い込まれても、それを上回る勢いで新たなネガティブが現れていったその後の状況においては、ごく小規模の残党に対する対応は後手に回らざるを得なかった。また、ジャリュウ一族の構成員である邪悪竜やジャリュウ兵を生み出すことができるのはリュウオーンだけであり、そのリュウオーン亡き今、ジャリュウ一族の残党が勢力を盛り返す可能性は非常に低いとの判断もあった。
だが・・・目の前のリュウオーン二世は、邪悪竜らしき二体の怪人と、十体以上のジャリュウ兵たちを従えている。おそらく、これ以外にもまだ兵隊はいるだろう。どうやってここまで戦力を再び整えたのか・・・。
「王がいなければジャリュウは数を増やせない・・・お前たちが無警戒に等しかったのは、そう踏んだからであろう。確かに、部下が勝手に数を増やさぬよう、先王は自分にしかジャリュウを生み出せぬようにしていた。だがな・・・ジャリュウを生み出す力は、ジャリュウ兵にも備わっていたのだ」
「なに?」
「王がいる間は、ジャリュウ兵たちは遺伝子に仕組まれたロックによって、自ら仲間を増やすことはできなかった。だがそのロックは、王が倒れ、一族が存続の危機に瀕するほど数を減らしたときに外れるように、王によって仕組まれていたのだ。そして王の死後、まさにその仕組みは動き出し、ジャリュウは再びその数を増やしていった。そして数を増やしたジャリュウ兵たちは、互いに殺し合い、その果てに生き残った最も強き者が進化を遂げ、ついに新たな王が誕生した・・・それこそがこの余、リュウオーン二世なのだ!」
誇らしげに胸を叩きながら、リュウオーン二世は叫んだ。
「Thank you veeeery much。ご解説恐縮の至り。しかし、そんな仕掛けがあったとは。その往生際の悪さ、トカゲというよりゴキブリだな。だがな。俺にとっちゃお前らがトカゲだろうがゴキブリだろうが、そんなのはどうでもいいこった」
そう言いながら、ボウケンレイダーはカイシューターの銃口をリュウオーン二世へと向けた。
「俺はプレシャスの奪還専門のエージェント。お前らのような奴らからプレシャスを奪い返すのが仕事だ。その相手が誰だろうが、俺の知ったこっちゃない。さっさとその笛を渡しな。もっとも・・・渡したからって、見逃してやるつもりはさらさらないがな」
ボウケンレイダーの言葉に、リュウオーン二世の背後に控えるジャリュウ兵たちがいきり立つ。だが、リュウオーン二世は不敵に笑った。
「生憎だが、そういうわけにはいかんな。この笛は有効に利用させてもらう。先王の代より我ら一族の悲願である、竜による世界の支配のためにな。そして、貴様などに構っている暇はない」
リュウオーン二世がそう言った、次の瞬間
ドガァァァァァァァン!!
「!?」
突如爆発音が響き渡り、船体が激しく揺れる。さらに爆発は続き、見る見るうちに船が傾ぎ始めた。
「くそっ、爆弾を仕掛けてやがったか!」
「ズオンよ」
「ハッ」
リュウオーン二世が従える二体の邪悪竜のうちのもう一体は、紫色の鎧を身にまとい、その右腕自体が大砲となっていた。リュウオーン二世に呼ばれたその邪悪竜は、大砲を壁に向けると発砲した。砲声が轟いた次の瞬間、ブリッジの壁には巨大な穴が開いていた。
「見ているがいい。まもなくこの世界は、我ら竜のものとなるのだ!」
「待てっ!」
リュウオーン二世は黄金の鎧の邪悪竜の背に飛び乗ると、壁の穴から飛び立った。紫色の鎧の邪悪竜がそれに続く。ボウケンレイダーもそれを追おうとしたが、その前にジャリュウ兵たちの群れが立ちふさがり、蛮刀を振りかざして彼に襲いかかってきた。
「邪魔だっつーの!」
群れを成して襲いかかってくる凶暴なトカゲ怪人たちだったが、ボウケンレイダーの敵ではない。ダッシュナイダーの刃が閃き、切れ味鋭くジャリュウ兵の首を斬り落とす。カイシューターの銃口が火を噴けば、数体のジャリュウ兵がまとめて吹き飛ばされた。
「ったく、手間とらせやがって」
瞬く間に十数体のジャリュウ兵を始末したボウケンレイダーは、リュウオーン二世たちが飛び出していった穴から自らも飛び出そうとした。が、そのときである。
ドガァァァァァァァァァァン!!
「うわぁぁぁぁぁぁぁっ!!」
突如巻き起こった一際大きな爆発が、一瞬にしてボウケンレイダーの姿を飲み込んだ。その爆発はボウケンレイダーのみならず、船全体を巻き込み、その船体を木端微塵に四散させた。
「これでよい。一度は奴らに阻まれた我らの宿願、二度と邪魔することは許さぬ。参るぞ、ゴードン、ズオン」
「「ハッ」」
上空から満足げにその様を見下ろすと、リュウオーンはそう号令を下した。リュウオーン二世を乗せた黄金の鎧の邪悪竜は飛び立ち、すぐに紫の鎧の邪悪竜がその後を追って猛スピードで泳ぎ始める。あとには海上にバラバラになって散らばり、燃え盛りながら浮かぶ船の残骸だけが残された。
だが・・・
「・・・ったく。舐めた真似をしてくれるぜ。こんなもんで俺を始末できたと思ってんのかねぇ」
ザバリと水しぶきと共に、ダークグリーンのスーツに覆われた腕が残骸の一つの縁を掴むと、次の瞬間、水中から無傷のボウケンレイダーが浮かび上がった。ボウケンレイダーはそのまま残骸の上に上がったが、そのとき、レイダーブレスが音をたて始めた。
『また逃げられたようだな、ドレイク』
レイダーブレスから3D映像で姿を現すなり、ミスター・ボイスが開口一番そう言った。
「「また」はねぇんじゃねぇか。そんなにしょっちゅう逃げられてねぇっつーの」
『そう口を尖らせるな。さすがに今回は特殊なケースだ。私も君を詰問するつもりはない。むしろこの件で非があるのは私の方だ』
「おやまぁ・・・あんたがそんなことを言い出すとは、雪でも降るんじゃないか?」
『まさかあのジャリュウ一族が、ここまで勢力を盛り返していたとはな。生き残りがいるとは聞いていたが、所詮トカゲが数匹と侮っていた。私は今改めて自戒している。プレシャスを狙う害虫どもは、やはり根絶やしにしなければならない』
「・・・まぁ、反省するのは結構だがな。今はそれよりも、先にやらなきゃらならないことがあるんじゃないのか?」
『そうだな。奴らがかつてのジャリュウ一族と変わっていないのであれば、プレシャスを強奪する目的は、ダークシャドウのように転売目的などではない。自らプレシャスを使い、人類を滅ぼして世界を征服しようとするつもりだろう』
「ああ。実際、竜による支配がどうのこうのと言ってたしな。気になるのは、今回奪っていったのが「ドルイドの魔笛」だってことだ。どんな生き物でも操る力があるんだろう、あれ?」
『思い当たる節もある。かつてジャリュウ一族は、レムリア文明の生物兵器である「幻獣」を復活させて使役しようと企んだことがある。今回も同様のことを企んでいるとするならば・・・』
「何かどえらいものを蘇らせようとしている、ってことか・・・」
『そうなる前にあのトカゲどもを止めなくては。ドレイク、ただ奴らを逃がしたわけではあるまいな?』
「当たり前だ。こう見えて俺は抜け目ないんだぜ?」
そう言いながら右手を持ち上げるボウケンレイダー。雲に切れ目がのぞき始めた空から月光が差し、その手首からどこまでも伸びる細い糸のようなものを、キラキラと反射させた。
-2011年8月3日 ベーリング海・セントジョージ島-
ベーリング海に浮かぶ小島、セントジョージ島。
この島は全体がごつごつとした黒い岩肌で覆われ、緑と言えばわずかに地面にへばりつくようにある地衣類程度であり、木は一本も生えていない。ほぼ一年を通して冷たく強い風が吹き荒れる環境は過酷であり、人間はおろか海鳥一羽住みついていない不毛の地である。
が・・・今、その不毛の地を踏みしめ歩く一団の姿があった。そして、それは異形の者たちである。多数のジャリュウ兵たち、そして部下である邪悪竜ゴードン、ズオンの二体を従え、リュウオーン二世が悠々と足を進める。
と・・・やがて彼らは、島のほぼ中央にそそり立つように位置する大きな岩山の前で足を止めた。
「・・・ここだ」
片手に持つ古びた手帳と目の前の岩山を見比べながら、リュウオーン二世は言った。
「やれ、ズオン」
「承知」
ズオンはリュウオーン二世の前に進み出ると、右腕の大砲を岩山へと向けた。
ドォォォォォォォォォォォン!!
砲弾が岩山を直撃するとともに、轟音が響き渡る。そして、立ち込めた砂煙が収まると・・・岩山の壁には、地面の下へと続く明らかに人工物と思われる階段の姿が露わとなっていた。
「おお・・・!」
それを目の当たりにしたジャリュウ兵たちの間からどよめきの声が漏れる。
「先王の遺した記録の通りだ。疑っていたわけではないが・・・これでようやく安心できるな」
「この下に眠っているのですな、「黄金の邪竜」・・・その魂が」
「しかし、なぜ先王はその在り処まで突き止めながら、手に入れようとなさらなかったのか・・・」
「邪竜の復活には「魂」と「体」が必要だ。既に本来の「体」が失われた以上、代わりの器となる「体」が必要だが、先王はそれにふさわしいものを見付けることができなかったのであろう。今となっては、正確なところはわからぬがな・・・」
「先王も成し得なかった偉業を陛下が成し遂げれば、先王もお喜びになるでしょう。さぁ、早く「魂」のもとへ」
「お前たち、先導しろ」
「ギィッ!」
ズオンに指さされたジャリュウ兵二体が先導となり、松明を掲げながら階段へと足を踏み入れ、リュウオーン二世らがそれに続く。階段はかなり長いものだったが、5分ほど下り続けたところでそれは終わり、平坦な一直線な通路へと出る。そのまま一行は歩みを止めずに進み続けた・・・が
ジャキンッ!!
「ギャァアアアアアアアアアア!!」
突如、壁と天井から突き出した鋭い鉄の棒が先導のジャリュウ兵たちの体を貫き、ジャリュウ兵たちの断末魔が通路に木霊した。
「フン、やはりトラップが仕掛けられていたか」
リュウオーン二世はそう鼻を鳴らすと、手にした剣をひと振るいした。通路をふさいでいた鉄の棒が、それに串刺しにされた哀れなジャリュウ兵たちもろとも粉々に砕け散る。
「次はお前たちだ。先導に立て」
「ギッ・・・!」
ズオンに指さされた別のジャリュウ兵たちが、たじろぎ後ずさる。
「・・・なぜ恐れる? ジャリュウ一族による世界支配の礎となれるのだぞ、光栄に思わんか。それとも・・・」
ゴードンが両翼に備える鋭いカッターを閃かせると、恐れをなしたジャリュウ兵たちは先頭へと進み出た。
「それでよい。さぁ、先を急ぐぞ」
そうして一行は、再び進み始めた。
リュウオーン二世たち一行の進む先には、さらにいくつものトラップが待ち受けていた。壁から吹き出す高熱のガス、天井から降り注ぐ灼熱の溶岩、突如床に開く奈落のような穴・・・そのたびに先頭に立つジャリュウ兵たちを犠牲にしながら、一行はついに目的の地へとたどり着いた。
「おおっ・・・!」
突如目の前に開けた光景に、一行の口から驚きの声が漏れる。
そこは広大なドーム状の空間だった。壁面にはびっしりと壁画と古代文字が彫り込まれており、漂う静謐な空気から、ここが神聖な場であることを無意識に感じさせる。壁のあちこちには竜の頭を模した彫刻が突き出しており、その口から清らかな水が静かな音をたてながら、その下にある池へと流れ落ちていた。
「間違いない。ここに「邪竜の魂」は封印されている」
「そのようですな。しかし、肝心の「魂」は・・・」
「あれを見ろ」
そう言ってリュウオーン二世は、この巨大な部屋の中央を指さした。石で造られた四角い構造物・・・一見して祭壇のように見えるものが、そこに屹立している。そしてその背後には、蝙蝠のような翼を背中に広げた美しい巨大な女神像がそびえ立っていた。
「おそらくあそこだ。だが・・・」
「妙なものがいくつも張り巡らされていますな・・・」
その祭壇と女神像を中心として、同心円状に光の壁が幾重にも張り巡らされている。
「結界だな。一つ一つを破壊するのは難しいことではないが、こう幾重にも張り巡らされていたのでは、破るにも時間がかかりそうだ」
リュウオーン二世がそう言った、そのときだった。
「!? 陛下ッ!!」
突如、ゴードンとズオンがリュウオーン二世の盾となるように動いた。その直後
ドガガガガガガガガァァァァァァァン!!
彼らの周囲で爆発が巻き起こり、多数のジャリュウ兵たちが悲鳴を上げながら木端微塵に吹き飛んだ。そして・・・
「Nobody expects the Spanish inquisition!!」
部屋の入り口から、カイシューターを手にしたボウケンレイダーが姿を現した。
「貴様・・・どうしてここへ!?」
「どうしてもなにも・・・案内してくれたのはおたくらだぜ。そこの紫の鎧のトカゲさん、右の手首を見てみな」
「なに・・・!?」
ズオンが右手首をよく見てみると、そこには髪の毛よりも細い糸が巻き付いており、それはボウケンレイダーへと向かって伸びていた。
「その糸・・・プレシャスか」
「そういうこと。こういうふうに逃げた奴を追っかけるのに重宝しているよ。しかし・・・追っかけてきてみりゃ、なんだろうねここは。結構遺跡は見て回ってきたが、そこの壁に書かれてる壁画といい文字といい、まるで見たことのないものばっかりだ」
周囲を興味深そうに見回しながら、ボウケンレイダーは言った。
「ここは一体何なんだ? ここへ来た目的ともども、教えてくれると助かるんだがな」
だが、その問いに答える代わりに、ズオンが一歩前へと進み出た。
「陛下、ここは私が引き受けます。その間に結界を破り、「邪竜の魂」を・・・」
「ズオン・・・」
「このような小細工に気付かず、奴をここまで招きよせたのは我が責任。どうか私に、この恥を雪ぐ機会をお与えください」
「・・・お主の決意、しかと見届けた。頼むぞ、ズオン」
「陛下は私がお守りする。存分にやれ」
「ありがたき幸せ・・・陛下を頼むぞ、ゴードン」
そう言うとズオンは、ボウケンレイダーを睨めつけた。
「サージェスの飼い犬ごとき、陛下の邪魔はさせん。ここから先はこの海竜騎士ズオンが、一歩も通さんと知るがいい!」
「トカゲのくせに忠義者じゃねぇか。だが悪いな、お前らはここで皆殺しと決まってるんだ。トカゲの血で汚すにはもったいない場所だがな」
「ほざけ、ここは貴様の墓場だ!」
ドンッ!
叫ぶのとほぼ同時に、右腕の大砲を発射するズオン。その攻撃を予期していたボウケンレイダーは横へと飛び退きながらカイシューターのトリガーを連続して引いた。銃口から発射された光弾を、ガードを固めて防ぐズオン。だが・・・
ドンドンドンッ!!
その隙にボウケンレイダーはカイシューターをリュウオーン二世へと向け、トリガーを引いた。発射された光弾は一直線にリュウオーン二世へと向かって走ったが・・・
「フンッ!!」
その間に割って入ったゴードンが両翼を振るってそれを弾き、弾き飛ばされた光弾は壁に当たって爆発した。
「す、すまぬゴードン! 貴様! 今相手をしているのは私だぞ!」
激昂してボウケンレイダーに叫ぶズオンだったが、ボウケンレイダーはカイシューターを片手でクルクル回しながら言った。
「なに勝手に決めてんだよ。今やってるのは所詮殺し合いなんだ。ましてや人同士ならいざ知らず、人とトカゲの殺し合いにルールなんざあるもんかよ」
「ヌ、ウゥ・・・おのれ、戦士の風上にも置けぬ奴め!!」
「戦士なんかじゃねぇっての。ったく、どいつもこいつも・・・俺がこんなスーツを着てるからって、勝手に正義の味方扱いしやがって」
「いいだろう。貴様がそう言うのならこちらも手段は選ばん。ゆけ、ジャリュウたち!!」
ズオンの号令と共に、背後に控えていたジャリュウ兵たちが一斉にボウケンレイダーへと襲いかかった。
「そういう単細胞だからトカゲだっつってんだよ」
少しも慌てる様子を見せず、カイシューターをホルスターに収めダッシュナイダーを引き抜くボウケンレイダー。直後、蛮刀をふりかざしたジャリュウ兵たちが襲いかかってきたが、それが振り下ろされる前に彼は一体目の胴を薙ぎ、二体目の喉笛を掻き斬り、三体目の鳩尾に刃を突き立てると、そのまま刃を押し下げて腹から股間までを掻っ捌いた。
「おのれぇっ!!」
その間にさらにもう一体が左から襲いかかったが、ボウケンレイダーはその右手首を掴みとると、ジャリュウ自身の突進の勢いを利用して難なくジャリュウをその場に叩き伏せた。背中から床に叩きつけられくぐもった呻きを発したその喉に、すかさずボウケンレイダーは足を振り下ろし、ゴキゴキと音をたてて首の骨をへし折った。
「ちょっと借りるぜ」
つかんだままだった右手に握られていた蛮刀を手に取ると、彼はそのままくるりと振り返りながらそれを背後に投げつけた。狙うでもなく無造作に投げられたそれは、背後から彼に襲いかかろうとしていたジャリュウ兵の眉間へと突き刺さり、断末魔を上げることなくジャリュウ兵はその場に倒れた。その後もジャリュウ兵たちは次々に襲いかかるが、指一本触れることもできずにボウケンレイダーの容赦のない攻撃の前にバタバタと倒れていった。
「ええい、時間稼ぎにもならんとは!」
「どうした、もうおしまいか? こないんだったらこっちからいくぜ」
「人間風情が、のぼせるな!」
右腕の大砲を連射するズオン。ボウケンレイダーはクルクルと回転してそれをかわし続けるが、なぜか反撃しようとはしない。
「どうした! かわすのが精一杯か!」
大砲を連射し続けるズオン。だが・・・
「数撃ちゃいいってもんじゃねぇんだよ」
バッ!
突如ボウケンレイダーは空中高く飛び上がると、カイシューターを両手で構え、ズオンに狙いを定めた。
「チャージ完了だ。くらいな、ファルコネット・バスター!!」
ドンッッッッッッッッ!!
「な、なにぃっ!?」
超特大のエネルギー弾がカイシューターの銃口から発射された。
ドガァァァァァァァァァン!!
「グワァァァァァァァァッ!!」
エネルギー弾が直撃し、派手に吹き飛ばされるズオン。背中から壁に激突し、地面へと落下したが、ボウケンレイダーは攻撃の手を緩めない。
「もらった!」
着地するや否や、ダッシュナイダーを構えて突進するボウケンレイダー。ズオンは地面に倒れたまま、まだ動かない。
だが・・・
ビュルルルルルルッ!!
「なにっ!?」
突如、ズオンの体から何かがすさまじいスピードで伸びてボウケンレイダーの体に巻き付き、その動きを完全に封じてしまった。
「残念だったな。所詮人間でしかない貴様には、このような攻撃は予測できまい」
ボウケンレイダーの目の前で、ズオンの頭が勝ち誇ったようにそう言う。なんとズオンは首をろくろ首のように長く伸ばし、ヘビのようにボウケンレイダーの体に巻き付いたのだ。
「このまま締め上げてくれる。全身の骨という骨をバラバラに砕かれるのが先か、窒息死するのが先か、どちらだろうな?」
その言葉通り、ものすごい力でボウケンレイダーを締め上げるズオン。ボウケンレイダーの体から、ミシミシと軋むような音が上がる。
だが・・・
「・・・ヘッ」
ボウケンレイダーの口から、嘲笑うような声が漏れた。
「貴様・・・何がおかしい!」
「残念だったな。所詮トカゲのてめぇには、こんな攻撃は予測できねぇだろ」
ボウケンレイダーがそう言った、その直後
ゴオオオオオオオオオオオオオッ!!
一瞬にしてボウケンレイダーの体が、焼けた鉄のように真っ赤に光り輝き、すさまじい高熱がその全身から放射された。
「ギャアアアアアアアアアアアッ!!」
密着していたがゆえに、まともにその高熱を首全体に受けたズオンは、反射的に拘束を解いた。
「き、貴様ぁ! 一体何をした!?」
「いちいちトカゲに説明する義理はねぇな」
ボウケンレイダーはにべもなくそう言うと、ダッシュナイダーを構えてズオンへと突進した。首全体が焼けただれ、伸縮性を失ってしまった今、長く伸びた首を戻せないズオンは思うように身動きが取れなかった。そして・・・
ドスッ!!
「グオオオオッ!!」
ダッシュナイダーの刃がズオンの鎧を貫き、胸元に深々と突き刺さる。さらに
「ドラゴン・トゥース!」
ドンッ!!
突き刺したダッシュナイダーの柄を、片手で打つボウケンレイダー。その瞬間、刀身を通じて強力な振動波がズオンの体内へと送り込まれる。振動波はズオンの体内を一瞬にして駆け巡り、その細胞の一つ一つを激しく揺さぶって細かく破砕し、ズオンは絶叫すら発することなく、細かな砂の山となって崩れ落ちた。
「・・・やれやれ。強力なのはいいが、やっぱりプレシャスの力なんざ使いたくはねぇな」
そう呟きながら、レイダーブレスを見やるボウケンレイダー。そのディスプレイには、「The Scale of Salamander」と表示されている。
長年にわたりプレシャスの回収と研究を続けてきたサージェス財団は、近年その成果として、一部のプレシャスの力の秘密の一端を解明し、それを科学の力で再現できるところにまでこぎつけている。そしてボウケンレイダーの最新型アクセルスーツには、その成果の一つが装備として搭載されていた。「プレシャス・フィードバック・システム」、略称「PFS」。プレシャスの力を再現し、探索や戦闘のために役立てることが可能なシステムである。
先ほどズオンの首に巻きつかれたときにボウケンレイダーが使用したのは、「サラマンダーの鱗」という名のプレシャスの力である。「サラマンダーの鱗」とは、その名の通り、炎の力を司る小型のドラゴン・サラマンダーの鱗であり、膨大な熱を発することができる。これはサージェス・ジャパンのボウケンレッドが使用する強化装備にも組み込まれているものだが、ボウケンレイダーは高熱を放射するその本来の力を持って、体に巻き付いたズオンを逆に焼いたのだった。
「さて、と・・・」
ボウケンレイダーはすぐに頭を切り替え、視線をリュウオーン二世とゴードンへと向けた。すると・・・
「ヌゥンッ!!」
まさにそのとき、祭壇を幾重にも取り巻いていた結界の最後の一つが、リュウオーン二世の振り下ろした剣によって粉々に破壊された。
「チィッ!!」
すぐさまそれ以上の行動を止めようと、猛然と走り出すボウケンレイダー。だが・・・
バリバリバリバリ!!
ゴードンが口から稲妻を放ったことで、ボウケンレイダーは足止めを余儀なくされた。
「陛下、今のうちに!」
「うむ」
ゴードンがボウケンレイダーの足止めをしている間に、リュウオーン二世は祭壇の前へと駆け寄った。
「さぁ、黄金の邪竜の魂よ。今こそ余の面前に姿を現すがよい!」
おもむろに祭壇の前に立つと、リュウオーン二世は手にした剣で、もう片方の手のひらを自ら切った。たちまち傷口から溢れたどす黒い血が、祭壇の上にだらだらと流れ落ちる。祭壇の表面は皿のようにくぼんでいて中央に穴が開いており、流れ落ちた血はその穴を通じて祭壇の中へと流れ落ちていった。すると・・・
ゴゴゴゴゴゴゴゴゴゴゴゴゴ!!
「うわっ!?」
突如、激しい地鳴りがその場にいた者たちを襲った。それはすぐに収まったが・・・
ガラガラガラガラ!!
その直後、リュウオーンの目の前で祭壇にひびが入り、瞬く間に崩れ落ちた。そして・・・
ズズズズズズ・・・
崩れた祭壇の下から、何かがゆっくりとせり上がってくる。それは、竜の足のような形をしたオブジェであり、その足に、何かが掴まれているのがボウケンレイダーには見えた。そのとき、レイダーブレスがけたたましい音を発した。ハザードレベルが高い・・・すなわち、危険なプレシャスが近くにあることを感知したのだ。そして、その計測されたハザードレベルの数値を見て、ボウケンレイダーは仰天した。
「ハザードレベル・・・600だと!?」
これまでにサージェス財団が回収に成功したプレシャスは、そのほとんどがハザードレベル100~200代のものであり、300を超えるものはドレイクもいまだに数えるほどしか出会ってはいない。ハザードレベル600ともなれば、もはや冗談抜きで世界を滅ぼすことのできる力をもっているプレシャスということになる。
ボウケンレイダーは、例の竜の足のオブジェに掴まれたものに視線を向けた。プレシャスの反応は、紛れもなくあれから発せられている。それは、「珠」であった。大きさは野球ボール程度で表面には傷一つなく、全体から黄金色の光を放っている。その光の美しさは見る者を魅了せずにはいられないものだったが、熟練したトレジャーハンターとしてドレイクが磨き続けてきた勘は、それがとてつもなく危険なものであるという警鐘を鳴らし続けていた。見た目こそ美しいが、あの珠はその美しさの影に底知れぬ邪悪さを隠し持っている。ドレイクはそう直感した。そして・・・
「フ・・・フハハハハハハハ! ついに手に入れたぞ、黄金の邪竜の魂を!」
リュウオーン二世はその珠を鷲掴みにすると、頭上に掲げて高笑いをあげた。
「させるか!」
それをリュウオーン二世の手から奪い返そうと、強引にでもゴードンを突破しようとボウケンレイダーが動きかけた、そのときだった。
ヴンッ!!
崩れた祭壇の後ろに立つあの女神像が、突如両目を赤く光らせた。それはすぐに消えたが、その直後、再び点灯する。そのように女神像は両目を点滅させ続けたが、いきなりその全身に稲妻のようにヒビが入った。そして、その直後
ドガァァァァァァァァァァァァン!!
「うわっ!?」
女神像は内部から、大爆発を起こして粉々に飛び散った。一体何が起こったのか。リュウオーン二世もゴードンも、そしてボウケンレイダーも、思わず砕け散った女神像を見つめて動きを止めた。そのときだった。
「そなたたちか。邪竜の魂の封印を解いた不届きものめらが」
声が聞こえた。まだ幼さの残る、少女の声である。いや・・・聞こえたというのは正確ではない。その声は音として耳を通して「聞こえた」のではなく、彼らの頭の中に直接「響いた」のである。そして・・・崩れた女神像から立ち上る粉塵の中から、小柄な影が姿を現した。
燃えるような紅い色をした髪を長く伸ばした少女が、その髪よりもさらに紅く透き通った目から走らせる視線で、その場にいる全ての者たちを射すくめた。